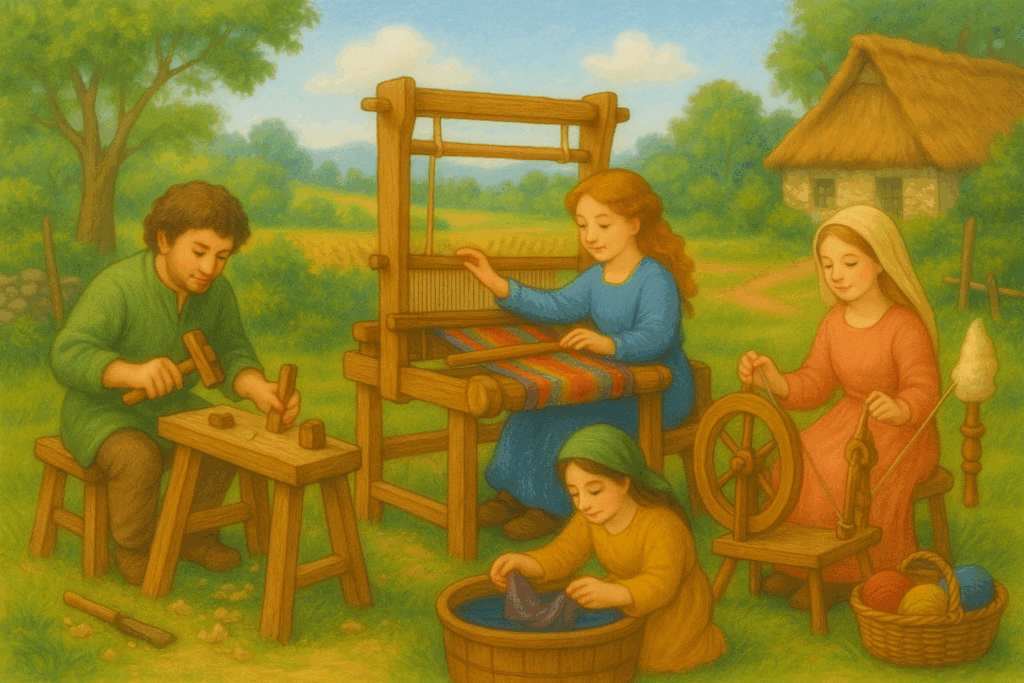
人類は、産業革命を境に、世界の在り方を大きく変えた。
それまで人の手や自然の力に委ねていた「ものづくり」は、
動力という新しい翼を得て、爆発的な生産の時代へと移行した。
宇宙月の流れで見るならば、
この200年は「地の時代」とも呼べる、物質が主役の時代だったのだと思う。
はじめ、人々は、便利な道具を手にして喜んだ。
生活が楽になり、世界が広がったように感じた。
それは確かに、ひとつの“進化”だった。
けれど、いつからだろう。
「満たされるために持つ」のではなく、
「不安を隠すために持つ」ようになったのは。
物は、いつの間にか、
生きるための伴侶ではなく、
優位を競うための記号へと変わっていった。
持っても満たされず、
飽きるとすぐに捨て、
壊れたら直すという発想すら失われていく。
その結果、地球のどこかで生み出されたものが、
別の場所で山のように捨てられるという、
不思議で、どこか歪な世界が出来上がってしまった。
資源は減り、
ゴミは溢れ、
誰かの「便利」の裏側で、
誰かの過酷な労働が当たり前のように組み込まれていく。
私たちは今、
この構造そのものが、限界に近づいていることを感じている。
けれど、環境問題は、
どこか遠くの偉い人たちが研究して解決する“特別な課題”ではなく、
日々の選択や、心の在り方そのものと、深く結びついているように思う。
尽きない欲望。
他人と比べる心。
創造することを忘れたまま、
消費することで自分を埋めようとする習慣。
もし、この「内側の飢え」に気づくことができたなら、
環境問題は、ほんの少しだけ、違う光のもとで、
見え始める気がしている。
だから私は、
「ゴミ」に目を向けたいと思った。
捨てられてしまった素材。
もう役に立たないとされた布。
誰にも見向きされなくなったものたち。
そこには、
かつての時間があり、
誰かの暮らしがあり、
確かに存在した“温度”が残っている。
私はそこに、
もう一度、物語の居場所をつくりたい。
ゴミから、アートを生み出すこと。
廃材から、暮らしの道具を生み出すこと。
それは「リサイクル」ではなく、
「私たちは、まだ作れる」という記憶を、
ひとつずつ取り戻す営みだと思っている。
豊かさとは、
持つことではなく、
生み出せる感覚の中にあるのではないか。
共存とは、
奪わないことではなく、
分かち合えることなのではないか。
私は、
正解を示したいのでも、
誰かに何かを強制したいのでもない。
ただ、
「こういう道もある」と、
ひとつの灯りを置いているだけだ。
ゴミの中から、
新しい世界の芽が生えることを、
静かに信じながら。
